過去の故障時の連続送信を再現
【米国(CHINA) vs 中華 vs 日本】
【ディレーティングカーブ Tc-Io(ケース温度-出力電流)】
【追記 シリコーングリスの塗り方が原因かも?】
これまで4回もブリッジダイオードを交換する羽目になりましたが、代替品は4個とも中華製です。
破壊の原因をいろいろ考察してみますが、その根本はブリッジダイオードの素性にあるのかもしれません。
過去の故障時の連続送信を再現しながら、実際の温度を観測するのがベストだと思いますが、残念ながら測定センサーを持っていません。
そこで、3種類の連続送信試験を行い、GSV-3000の電源OFFから【サーモスイッチによる空冷ファンOFFディレイ】で自動的にファンが停止するまでの時間を測定し、簡易的にヒートシンク部の過熱状態を比較してみます。
ただし、現在は電源ONで高速回転しますので、相対的なことしか言えません。

最初に壊れたブリッジダイオードですが、横に印刷してある内容から『①のVishay Intertechnology製』だと思われます。
購入から3年目(2021年1月)、オーディオアンプのインターフェア試験でCWキャリア100W連続送信を長時間繰り返した後、即座に電源OFFしたため冷却不足となり昇天しました。(空冷ファンOFFディレイ未設置)
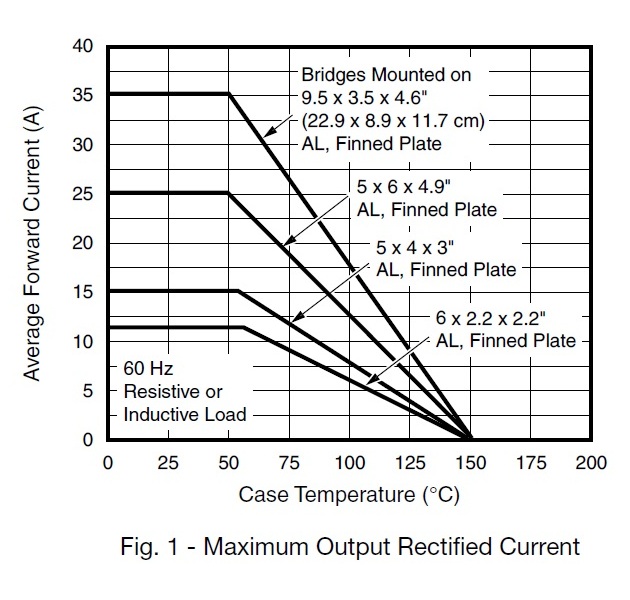

①GSV-3000素子同等品
米国 (CHINA)
メーカー Vishay Intertechnology
GBPC3504、35A 400V
温度ディレーティングは、30Aで約70℃
RS-onlineで@738
【再現試験 A】
14MHz CWキャリア100W連続送信⇒3分間 ⇒IC-7610電源OFF⇒GSV-3000電源OFF
⇒空冷ファンOFFディレイ作動 ⇒自動停止時間 3分45秒
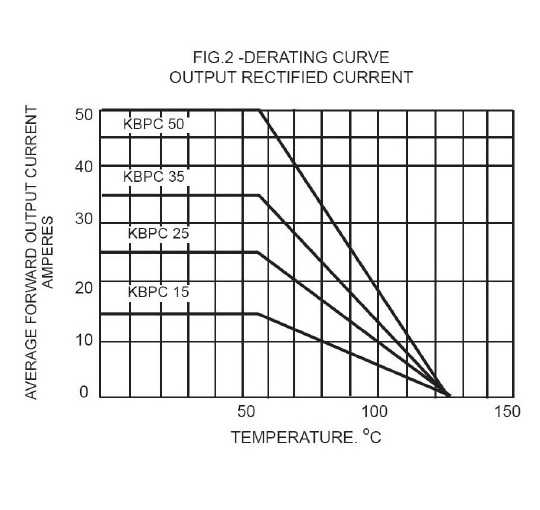
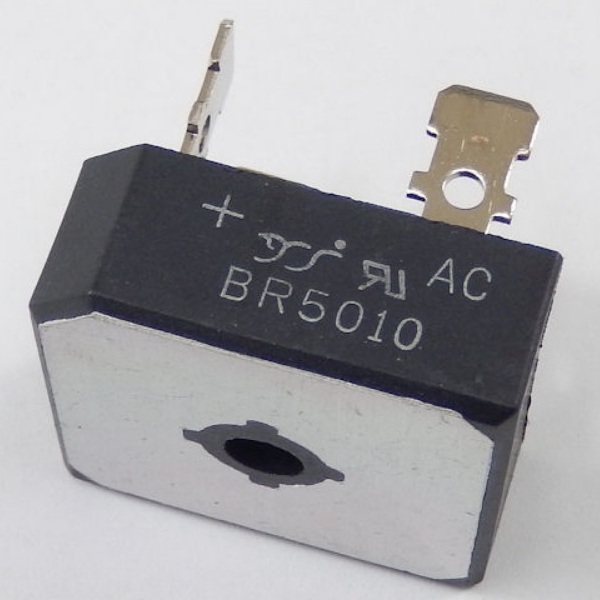
②故障時の代替品、中華製
メーカー Yangzhou Yangjie
KBPC BR5010、50A 1000V
温度ディレーティングは、30Aで約83℃
秋月電子で、@300
オリジナル素子が35Aで定格ギリギリだったため、代替品として購入しました。
2度目の故障は、日常のFT8長時間運用後の電源OFF時。
3度目の故障は、8月のSSTVコンテストでの長時間運用後の電源OFF時。(2020年コンテストは無事だった)
(いずれも空冷ファンOFFディレイ未設置)
【再現試験 B】
3.5MHz FT8 連続運用⇒30分間 ⇒IC-7610電源OFF⇒GSV-3000電源OFF
⇒空冷ファンOFFディレイ作動 ⇒自動停止時間 3分
その後「空冷ファンOFFディレイ」を設置し、快適に運用。していたはずが、4度目の故障。
前記事のとおり、Scottie1モード送信途中で、驚愕の破裂。
【再現試験 C】
14MHz SSTV Scottie1モード2回連続送信⇒4分間 ⇒IC-7610電源OFF⇒GSV-3000電源OFF
⇒空冷ファンOFFディレイ作動 ⇒自動停止時間 5分15秒
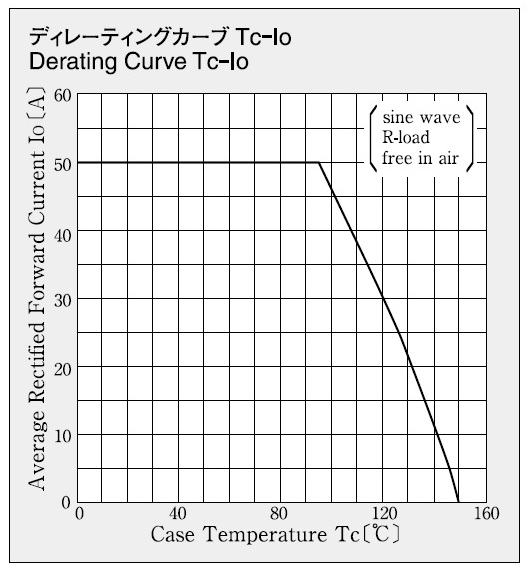

③今後の候補品、日本製
メーカー 新電元工業
S50VB60、50A 600V
温度ディレーティングは、30Aで120℃
RS-onlineで、@2,460
もしも5度目壊れたら、最有力候補の日本製です。(ちょっと高価ですが)
形状・寸法・ネジ位置が異なるので、工夫が必要です。(カイショウ)
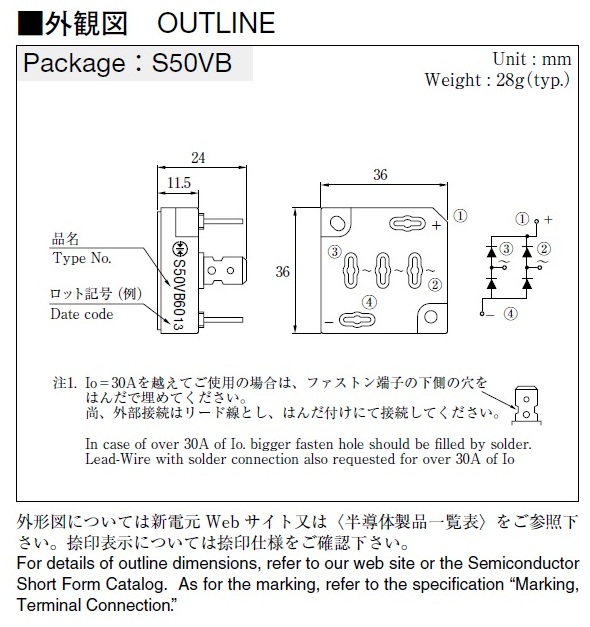

④ファストン端子
Io=30Aを超える場合、外部接続はリード線とし、ハンダ付けにて接続
(Io=30A以下はファストン端子メス型の使用可)
実は、度重なるブリッジダイオード交換作業で、端子への太い配線が少しずつ短くなっていき、ハンダ付け処理の限界が近づいています。(苦)
GSV-3000の最大定格は「連続30A(13.8V時)8時間」となっていますが、IC-7610 100Wでは連続22Aです。
ということで、今後も度重なる交換が必要となったときには、ファストン端子を使おうかと考えています。
現状の「②KBPC5010 & 常時強制空冷 & 空冷ファンOFFディレイ」の組み合わせで長持ちしてくれるのがFBなんですが、これまでの経過から考えて中華製の劣化速度は不安です。
今度壊れるとしたら、4月頃・・・?(笑)
連続送信や長時間運用が続いた場合、肝心のIC-7610本体も冷えてから電源OFFした方が安全なので、シャックを離れる際には、もう5分間バンドサーフィンしてから全部の電源を落とすように心掛けたいと思います。(珍局が見つかるかもしれませんし・・・)
【追記 シリコーングリスの塗り方が原因かも?】
その後、CQ誌に記事を書かれているOMさんとQSOする機会があったので熱に関することを伺いました。
接合温度・熱抵抗・熱損失の関係など話していただきましたが、年老いた田舎のラジオ少年の勉強不足が露呈するばかり。(汗)
その中で、分かり安かったのは「シリコーングリスの塗り方」で、放熱を思うばかりに厚く塗りすぎると逆効果とのこと。
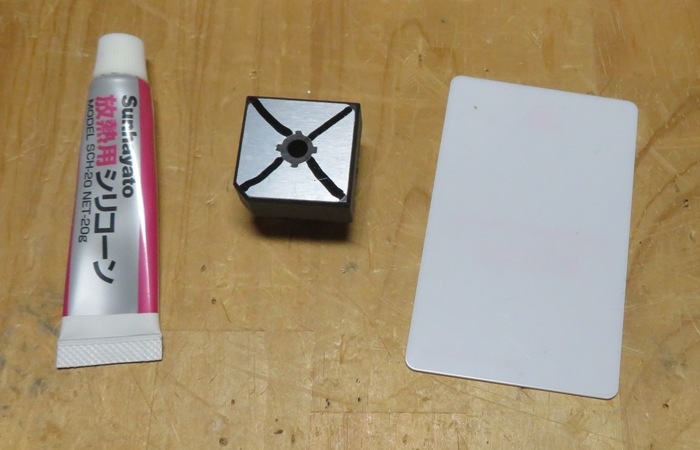
塗り方はシンプルで、塗布面(素子面とヒートシンク面)にマジックで×印を書いておき、その×印が薄く見える程度に塗るというものです。(なーるほど)
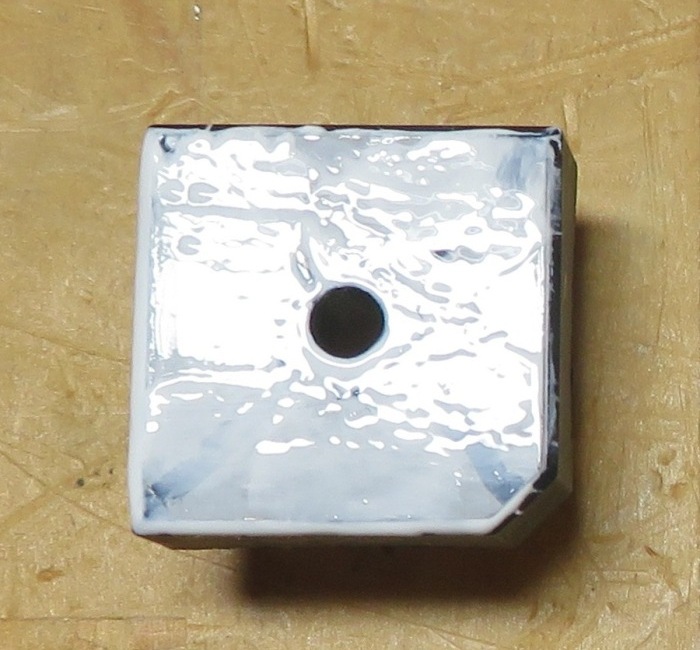
塗り方を試してみましたが、前回はこのくらい塗っていたかもしれません。
4回目の暴発は、厚塗りが主因だったかもしれません。(汗)
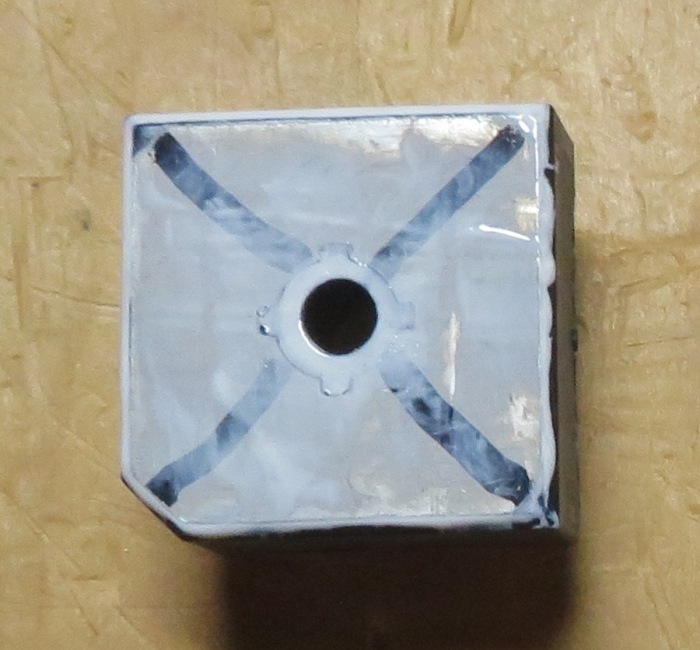
薄めのプラスチックカードで均してみましたが、ちょっと削り過ぎでしょうか?
【米国(CHINA) vs 中華 vs 日本】
【ディレーティングカーブ Tc-Io(ケース温度-出力電流)】
【追記 シリコーングリスの塗り方が原因かも?】
これまで4回もブリッジダイオードを交換する羽目になりましたが、代替品は4個とも中華製です。
破壊の原因をいろいろ考察してみますが、その根本はブリッジダイオードの素性にあるのかもしれません。
過去の故障時の連続送信を再現しながら、実際の温度を観測するのがベストだと思いますが、残念ながら測定センサーを持っていません。
そこで、3種類の連続送信試験を行い、GSV-3000の電源OFFから【サーモスイッチによる空冷ファンOFFディレイ】で自動的にファンが停止するまでの時間を測定し、簡易的にヒートシンク部の過熱状態を比較してみます。
ただし、現在は電源ONで高速回転しますので、相対的なことしか言えません。

最初に壊れたブリッジダイオードですが、横に印刷してある内容から『①のVishay Intertechnology製』だと思われます。
購入から3年目(2021年1月)、オーディオアンプのインターフェア試験でCWキャリア100W連続送信を長時間繰り返した後、即座に電源OFFしたため冷却不足となり昇天しました。(空冷ファンOFFディレイ未設置)
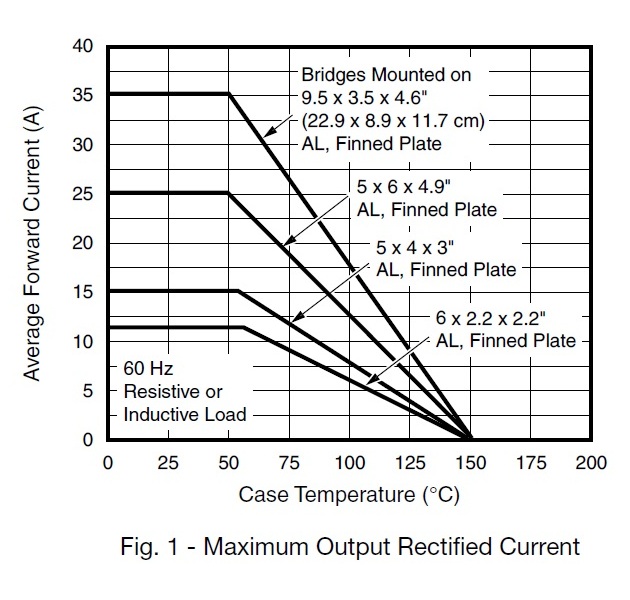

①GSV-3000素子同等品
米国 (CHINA)
メーカー Vishay Intertechnology
GBPC3504、35A 400V
温度ディレーティングは、30Aで約70℃
RS-onlineで@738
【再現試験 A】
14MHz CWキャリア100W連続送信⇒3分間 ⇒IC-7610電源OFF⇒GSV-3000電源OFF
⇒空冷ファンOFFディレイ作動 ⇒自動停止時間 3分45秒
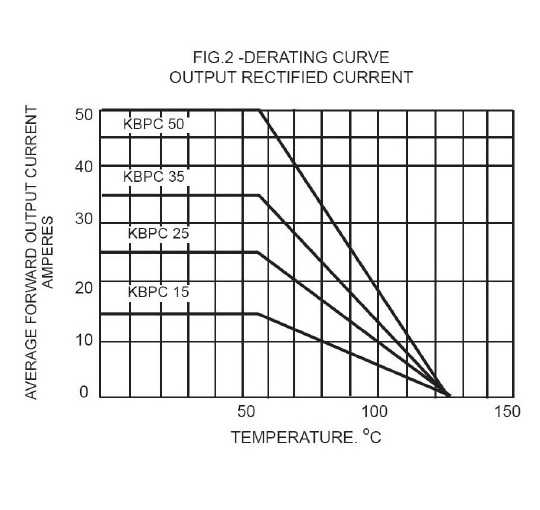
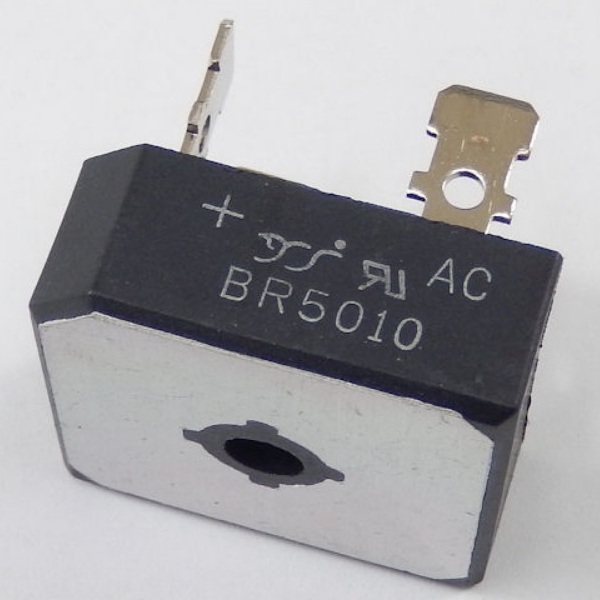
②故障時の代替品、中華製
メーカー Yangzhou Yangjie
KBPC BR5010、50A 1000V
温度ディレーティングは、30Aで約83℃
秋月電子で、@300
オリジナル素子が35Aで定格ギリギリだったため、代替品として購入しました。
2度目の故障は、日常のFT8長時間運用後の電源OFF時。
3度目の故障は、8月のSSTVコンテストでの長時間運用後の電源OFF時。(2020年コンテストは無事だった)
(いずれも空冷ファンOFFディレイ未設置)
【再現試験 B】
3.5MHz FT8 連続運用⇒30分間 ⇒IC-7610電源OFF⇒GSV-3000電源OFF
⇒空冷ファンOFFディレイ作動 ⇒自動停止時間 3分
その後「空冷ファンOFFディレイ」を設置し、快適に運用。していたはずが、4度目の故障。
前記事のとおり、Scottie1モード送信途中で、驚愕の破裂。
【再現試験 C】
14MHz SSTV Scottie1モード2回連続送信⇒4分間 ⇒IC-7610電源OFF⇒GSV-3000電源OFF
⇒空冷ファンOFFディレイ作動 ⇒自動停止時間 5分15秒
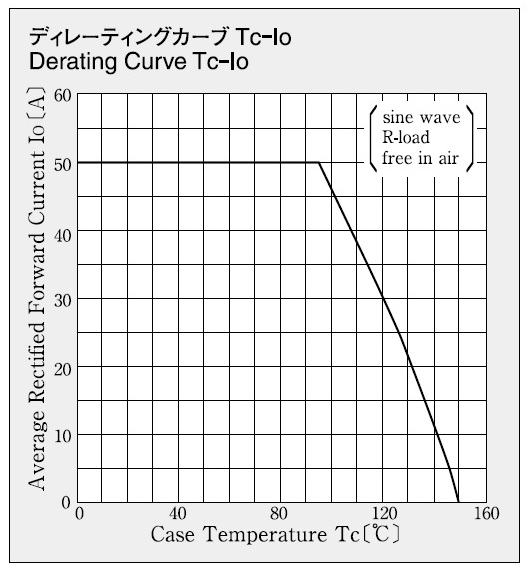

③今後の候補品、日本製
メーカー 新電元工業
S50VB60、50A 600V
温度ディレーティングは、30Aで120℃
RS-onlineで、@2,460
もしも5度目壊れたら、最有力候補の日本製です。(ちょっと高価ですが)
形状・寸法・ネジ位置が異なるので、工夫が必要です。(カイショウ)
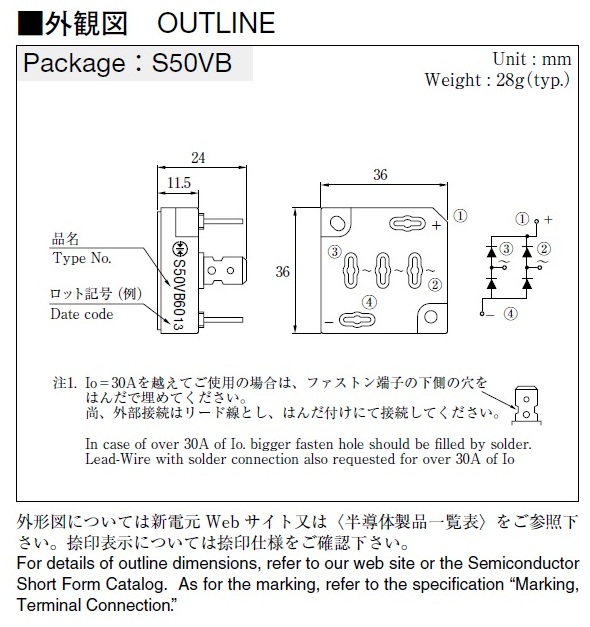

④ファストン端子
Io=30Aを超える場合、外部接続はリード線とし、ハンダ付けにて接続
(Io=30A以下はファストン端子メス型の使用可)
実は、度重なるブリッジダイオード交換作業で、端子への太い配線が少しずつ短くなっていき、ハンダ付け処理の限界が近づいています。(苦)
GSV-3000の最大定格は「連続30A(13.8V時)8時間」となっていますが、IC-7610 100Wでは連続22Aです。
ということで、今後も度重なる交換が必要となったときには、ファストン端子を使おうかと考えています。
現状の「②KBPC5010 & 常時強制空冷 & 空冷ファンOFFディレイ」の組み合わせで長持ちしてくれるのがFBなんですが、これまでの経過から考えて中華製の劣化速度は不安です。
今度壊れるとしたら、4月頃・・・?(笑)
連続送信や長時間運用が続いた場合、肝心のIC-7610本体も冷えてから電源OFFした方が安全なので、シャックを離れる際には、もう5分間バンドサーフィンしてから全部の電源を落とすように心掛けたいと思います。(珍局が見つかるかもしれませんし・・・)
【追記 シリコーングリスの塗り方が原因かも?】
その後、CQ誌に記事を書かれているOMさんとQSOする機会があったので熱に関することを伺いました。
接合温度・熱抵抗・熱損失の関係など話していただきましたが、年老いた田舎のラジオ少年の勉強不足が露呈するばかり。(汗)
その中で、分かり安かったのは「シリコーングリスの塗り方」で、放熱を思うばかりに厚く塗りすぎると逆効果とのこと。
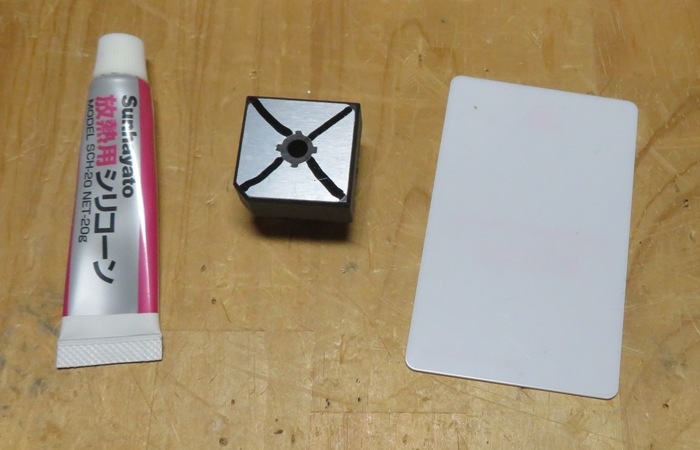
塗り方はシンプルで、塗布面(素子面とヒートシンク面)にマジックで×印を書いておき、その×印が薄く見える程度に塗るというものです。(なーるほど)
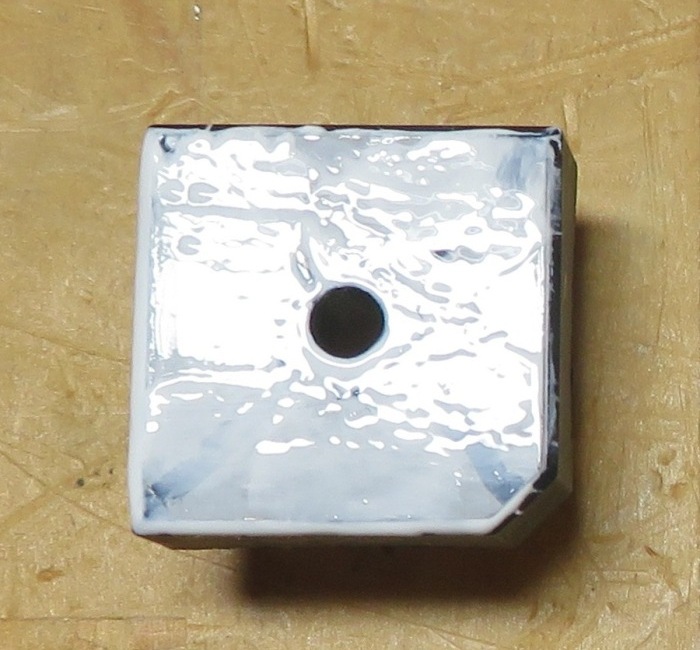
塗り方を試してみましたが、前回はこのくらい塗っていたかもしれません。
4回目の暴発は、厚塗りが主因だったかもしれません。(汗)
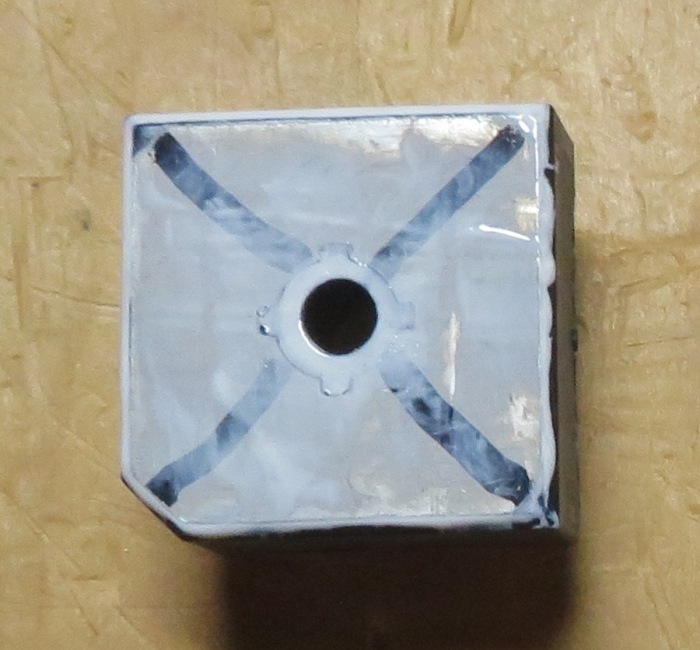
薄めのプラスチックカードで均してみましたが、ちょっと削り過ぎでしょうか?














コメントする