BBD測定まとめ
【ノイズのいろいろ】
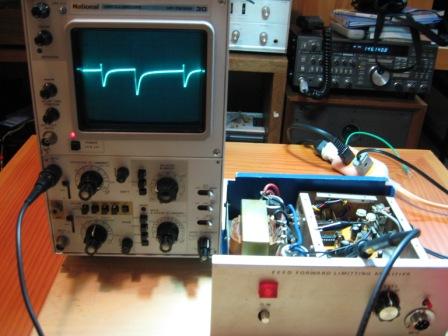
遡っての書き込み。(スミマセン)
クロック、LPF、電源ライン、BBD以外の素子、BBDの有無で測定したものをUP。
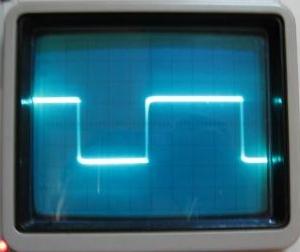
BBD MN3004のクロック。
MC14011 NANDゲートにより発生。
5V/DIV 2μS
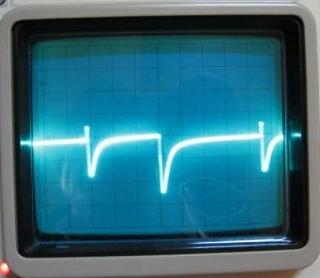
BBD出力でクロック成分をキャンセル。
0.5V/DIV 2μS
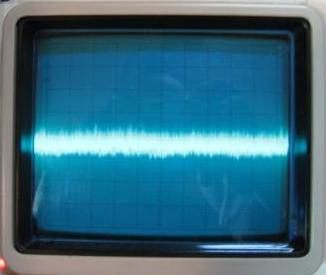
741 ザレンキー形アクティブLPF 約5KHz。
2mV/DIV

+15V電源ラインのノイズ。
2mV/DIV
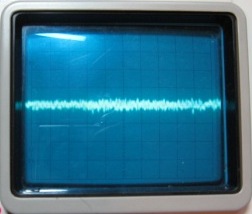
−15V電源ラインのノイズ。
2mV/DIV
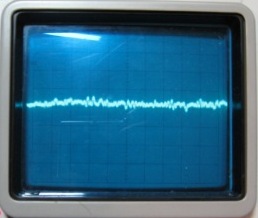
AN829S 電圧制御型ATTのノイズ。
2mV/DIV
実は、コントロール電圧を設定する半固定VRが、長い年月の間にガリオームとなっていたため、AN829Sを含むコントロール回路にノイズが乗り、結果としてセットノイズに現れていた。
これは、補修後のコントロール系のAN829Sのノイズ。
この他にも、素子単体の出力をあたってみると、それなりに残留雑音が出ている。
データシートでは、MN3004で雑音電圧0.21mVrms(0.59mVP-P)、AN829Sで0.15mVrms(0.42mVP-P)となっている。
ちなみに2号機で使われているNJM2114Dは、入力換算雑音電圧0.9μVrms(2.54μVP-P)である。

トータルでのセットノイズ。
2mV/DIV

試しにBBDを取り外し、in-outをスルーしたときのセットノイズ。
2mV/DIV
オーディオ機器に接続してのモニターでは、トータルで「ザー」という感じだが、BBDを取り外すと「サー」という感じになる。
シンクロ測定の、ブロープ1:1&10倍レンジの高感度測定では、ブロープのアースポイントによりインバータ蛍光灯ノイズなどの外部誘導を受けた。
なお、本セットのアナログ部とデジタル部のアースは混在している。
BBDのことばかり気にしていたが、素子の選別、アースパターン、部品の質、配線なども十分考慮しないとトータルノイズを減らすのは至難の技らしい。
年老いた田舎のラジオ少年には、難しい課題だ。
OMさんが発表してくれる作品を、何とか組み上げることができれば上等上等。(自分でなぐさめ?)・・・
【ノイズのいろいろ】
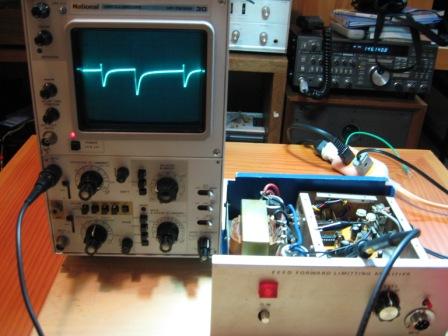
遡っての書き込み。(スミマセン)
クロック、LPF、電源ライン、BBD以外の素子、BBDの有無で測定したものをUP。
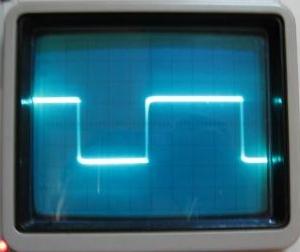
BBD MN3004のクロック。
MC14011 NANDゲートにより発生。
5V/DIV 2μS
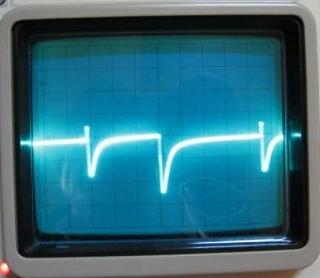
BBD出力でクロック成分をキャンセル。
0.5V/DIV 2μS
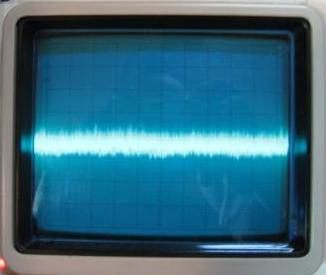
741 ザレンキー形アクティブLPF 約5KHz。
2mV/DIV

+15V電源ラインのノイズ。
2mV/DIV
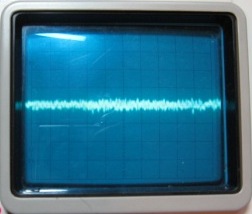
−15V電源ラインのノイズ。
2mV/DIV
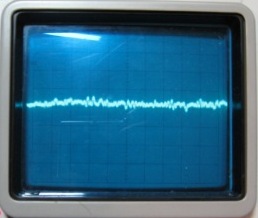
AN829S 電圧制御型ATTのノイズ。
2mV/DIV
実は、コントロール電圧を設定する半固定VRが、長い年月の間にガリオームとなっていたため、AN829Sを含むコントロール回路にノイズが乗り、結果としてセットノイズに現れていた。
これは、補修後のコントロール系のAN829Sのノイズ。
この他にも、素子単体の出力をあたってみると、それなりに残留雑音が出ている。
データシートでは、MN3004で雑音電圧0.21mVrms(0.59mVP-P)、AN829Sで0.15mVrms(0.42mVP-P)となっている。
ちなみに2号機で使われているNJM2114Dは、入力換算雑音電圧0.9μVrms(2.54μVP-P)である。

トータルでのセットノイズ。
2mV/DIV

試しにBBDを取り外し、in-outをスルーしたときのセットノイズ。
2mV/DIV
オーディオ機器に接続してのモニターでは、トータルで「ザー」という感じだが、BBDを取り外すと「サー」という感じになる。
シンクロ測定の、ブロープ1:1&10倍レンジの高感度測定では、ブロープのアースポイントによりインバータ蛍光灯ノイズなどの外部誘導を受けた。
なお、本セットのアナログ部とデジタル部のアースは混在している。
BBDのことばかり気にしていたが、素子の選別、アースパターン、部品の質、配線なども十分考慮しないとトータルノイズを減らすのは至難の技らしい。
年老いた田舎のラジオ少年には、難しい課題だ。
OMさんが発表してくれる作品を、何とか組み上げることができれば上等上等。(自分でなぐさめ?)・・・














コメントする